| 名前 |
コメント |
 名も無き修羅
名も無き修羅
2004/12/18 16:32

編集
|
[雑談]:駆徐???
十二月号のBasrrの記事だったのですが琵琶湖のバス駆徐に地元のボーイスカウトが参加!みたいな記事があったのですがボーイスカウトって小学生ですよね?大人でもなかなか正しい答えの出せない外来種問題に命の大切さをまず教えなければならない子供を協力させるというのはどうなんでしょ?まだ他にも問題はあるのでしょうが最近記事を読み返してゾッとしたので・・・
|
 year2003
year2003
2004/12/18 19:23
編集
|
Re :
琵琶湖ではありませんが、うちの地元でも農業用溜池のバス駆除に
教育委員会が小学生を駆り出してました。「小学生に生態系の大切さ
を教える良い機会になった」という、そもそも根本から大きく
間違っているコメントまで出していました。日本の教育はどうなんだ?
とちょっと心配になった記憶があります。
少なくとも近いうちに生まれる私の子供に関しては、私が公平な知識
を教えてあげるつもりでいます。
|
 xxxcool
xxxcool
2004/12/18 19:58
編集
|
Re :
長野では県知事が参加して釣り大会を開催し釣ったバスやギルを参加者がその場で調理した物を食べていたようです。(食べたのはギルだけかもしれません。)確かギルバーガーを食べていたように思ったのですが、これも不確かです。すいません。
その釣り大会の宣伝を知事自身がローカル局の県の広報番組で行っていました。
一見同じ駆除のようでも、その意味は大きく違いがあるように思います。
|
 L13
L13
2004/12/18 20:25
編集
|
Re :
釣りをしない人には農作物を荒らすイノシシ、ゴミを漁るカラス、在来種を食べるバス、みんな同じなんですよ。イノシシやカラスが駆除されても何も感じないようにバスの駆除=自然保護の図式に何の抵抗も感じないんだと思いますよ。子供にバスの駆除をさせる事は自然保護、子供の健全育成に役立つと考えているのでしょう。もう少し違う観点から考えてほしいものです。
|
 バモズ
バモズ
2004/12/18 21:04

編集
|
Re:
何で見たかは覚えてないのですが、滋賀県の小学生が「駆除される魚がかわいそう」という事を知事に言っていました。それで知事は、「いろいろ研究して駆除した魚を利用していきたい」と言ってました。滋賀県は駆除を続けていくようですね。
|
 xxxcool
xxxcool
2004/12/18 21:23
編集
|
Re :
表向きだけの発言に聞こえてなりませんね。
「駆除した魚を利用」しているのではなく「魚を駆除する事を利用」しているんじゃないでしょうか。
|
 バモズ
バモズ
2004/12/18 21:54

編集
|
Re:
xxxcoolさん、まとめていただきありがとうございましたm(__)mバサーの10月号に載ってました!外来魚を肥料や食べ物に有効利用する取り組みもすすめていきたいそうです。で今年の春、滋賀県の道の駅で外来魚の試食があり食べたのですが、味付けが濃くて魚の味はわかりませんでした(笑)
|
 doo
doo
2004/12/18 22:10
編集
|
Re :
琵琶湖もいずれバスがいなくなるんでしょうかねぇ・・・
話がずれますが、最近バス雑誌を久しぶりに見たら奥田さんが野池で釣りをしてる記事が載っててびっくりしました。琵琶湖のデカバスハンターだったのに・・・メディアに出てる人は条例違反できないですもんねぇ。
|
 へたれバッサー
へたれバッサー
2004/12/18 22:52
編集
|
Re :
あるサイトの抜粋です。
2月24日
◆正論か屁理屈か
滋賀県が今年のノーリリースありがとう券の引き換え額を1キロ100円と決定した。昨年は1キロ200円だったので、今年は半額となる。
このノーリリースありがとう券は、昨年も2ヶ月間実施された事業であり、外来魚であるブラックバスとブルーギルを指定された店舗に持ち込めば、100円のありがとう券が貰えるシステムとなっていた。
今年のように買取額を減額すれば、同じ予算で倍の回収が可能になるので効率的であるが、その一方で漁業者の買取額は一定のままだ。
2年前からの漁業者の買取額は通常期1キロ350円、アユの禁漁期1キロ500円となっている。
すなわち、今年の場合だと1キロの買取額が市民100円、漁業者500円となる。実にその差5倍である。
環境のための外来魚の駆除に、なぜ、額の差が必要なのだろうか?誰が駆除しても環境には同じ効果があるはずではないか?(そもそも外来魚を取り除けば生態系が守られるという根本自体が単純発想というか精神論にちかいのだが、ここではその点を無視して考えよう)
正論として漁業者の買取額も5分の1にすれば、5倍回収できるのだ。その点について、漁業者の視点に立つと、キロ350円以下になると刺し網や燃料代などの経費が賄えなくなるというのだ。だがら一定額以上の金額が必要になるという。
この理屈は理解できるのだが、環境のための効率的な除去が市民の方が安い経費で出きるのなら市民の買取額に予算を配分すればいいではないのか?
ちなみに今回の買取事業では市民へのノーリリース券「自然保護課予算800万円」漁業者の駆除事業「水産課予算1億2250万円」となっている。
その比率を自然保護課へ配分すればキロ100円で駆除するので駆除量が増えるはずである。もっとも単純なのは誰から買い取っても同額にするのが一番自然なのではないだろうか?
漁業者が効率的に駆除するという意見ももちろんあるだろうが、この数字を見れば、漁業者への外来魚被害への補償金として機能していると受け取られても仕方がないだろう。
事実、琵琶湖漁業のある組合では、「外来魚の駆除事業がないと喰ってはいけない」という声も聞こえるのである。外来魚がいなくなっても、在来魚の需要は伸びない。なぜなら、頼みの綱のアユは冷水病以降、各地の内水面組合では自前で種苗から養殖を始めてしまったのである。だから獲れても必要がないのである。だから売れないと予想される。食用としてもアユの佃煮、フナ寿司の需要がいきなり高まるというのは考えにくいのである。普通の市民はキロ500円の魚よりも、キロ300円のお肉を食べるだろう。ましてやキロ1000円を越えるモロコなど、キロ1000円を越えるお肉に対抗できるだろうか?海の魚に対抗できるだろうか?
そう考えると、琵琶湖の外来魚がいなくなった時、琵琶湖漁業はどうなるのだろうか?不必要な高価買取策が独自経営を阻害しているのは、農業、林業、漁業の共通点である。行政や政治は最後まで第1次産業を保護できるのだろうか?そんな責任も取らない行政や政治に頼っていることを怖いと思わないのだろうか?
責任所在の明確ではない施策ゆえに怖いのだ。もし、在来魚が○○年までに○○tの漁獲高にならなければ、担当課職員は解雇というルールでもあれば、もっと効率的な施策になるのではないだろうか?苦しい予算配分は理解できるが、小額予算で無駄に消えるぐらいなら実施しない方がマシだ。それを意思の表れという無責任は浪費をするべきではないと思う。
「琵琶湖の漁師も廃業しているし、あんらも仕方がない。」と某所で公務員からオフレコで言葉をかけられたのだが、その言葉に本質があるのだろう。言い換えれば、「私は安泰や」ということだろう。
せめてやるなら、レジャー産業(バス釣り産業)を殺すというのら、漁業ぐらいは守ってみろよと言いたい。全体の奉仕者よ。どちらも守れず殺して、給料だけ貰っているのは許せない。
「ノーリリース券」個人的には100円の券が欲しいとは思わないが、この買取額の差については納得できないのだ。その腹心にはこのような背景があるのだ。
皆さんはどうおもわれますか?
|
 名も無き修羅
名も無き修羅
2004/12/18 22:53

編集
|
Re:
皆さん色々な情報や意見ありがとうございます もう既にそうとう広がっている動きのようですねせめて僕の子供には命の大切さをしっかり教えていきたいです ところでバスの駆徐には助成金とかってでているんですかね?
|
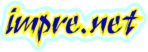
 このスレッドに返信する
このスレッドに返信する このスレッドに返信する
このスレッドに返信する